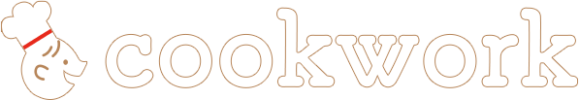ヒトがはじめて火を使って調理を始めたのは、いろいろ諸説はありますが「焼く」ことに関しては、約100万年前には始まっていたとされています。
そこから、「茹でる」「揚げる」「蒸す」などといった調理法が増えて、発展していきました。
今でも私たちの暮らしの中でこれらの調理法は使われていますよね。
そして、様々な文化ができて飲食店もどんどん増えてきて、今ではいろいろな料理を食べることができます。
その中で、化学・テクノロジーが進化した現代には昔の人からすれば驚くような新しい調理技術や飲食店が日々作られているのです。
今回は、そういった進化した最先端・未来の調理技術や飲食店についてお話ししてまいります。
化学とは、いろいろな物質を反応させてどう変わっていくかを研究する学問です。
「ばけがく」ともいわれるように、化学の力は別のものに変える・化ける魔法のようなものなのです。
そしてこの化学という魔法で新しい調理技術が開発されて、新しい料理がうまれました。
それでは、化学の力で進化した調理技術を紹介してまいります。
言葉の通りで、肉や魚などを低温でじっくり時間をかけて熱を加えていく調理法です。
低温調理された料理はとても柔らかくジューシーに仕上がります。
最近では飲食店だけではなく、自宅でも使われていますね。
実はこの低温調理も、化学の知識があるからこそできたものなのです。
そのポイントは「タンパク質」です。
一般的に肉を加熱調理すると、固くなりますよね?
これにはミオシンとアクチンというタンパク質が関わっています。
ミオシンは40℃くらいで変化をしはじめて旨味が増していき、アクチンは65℃くらいで変化をし始めて固くなり、パサついてしまう原因となります。
そこで、旨味が増していく40℃から、固くなってパサつきはじめる65℃までの温度でじっくり熱を加えて調理をしていけば、ジューシーで柔らかい肉料理ができるというわけです。

窒素というと空気の8割を占めるものですが、-196℃で液体に変わります。
調理の過程でこの液体窒素を加えると、素材の風味や食感を変えずに凍らせることができます!
この液体窒素は料理だけでなく、デザートにも使われます。
アイスクリームやムースを凍らせて、口の中でシュワっと溶ける新しい食感のデザートや、液体窒素が気化していき白い煙のようなものになるのを利用して、SNS映えを狙ったデザートもつくられています。
なにからなにまで「泡状」にする器具です。
…といってもいまいちピンときませんよね。(笑)
詳しく説明していきます!
たとえばですが、ハンバーグやシチューでも使われるデミグラスソース。
そのデミグラスソースをエスプーマにいれて、ゼラチンや卵白などの味に影響のない凝固剤も加えます。
そして、亜酸化窒素ガスという特殊なガスと一緒によく混ぜ合わせると、あら不思議!
デミグラスソース味で軽い食感の泡が出来上がるのです!
エスプーマの語源はスペイン語で、「泡」という意味からです。
もちろん、語源が生まれたスペインが発祥で、世界一予約が取れない超有名レストラン「エル・プジ(現在は閉店しています)」の料理長が開発しました。
さまざまなものをエスプーマにすることで料理の幅が広がり洋食だけでなく、和食でもごまのエスプーマ、ゆずのエスプーマなども作られています。
また、デザートでもエスプーマは使われており、昨今ではかき氷の上にエスプーマを乗せたものや、生クリームをエスプーマにしたものもよく見かけるようになりました。
ゼリーやプリンなどのゲル状の食べ物を作るときには寒天やゼラチンをつかうケースが多いですが、寒天やゼラチンを使うより透明度が高くなる「アガー」、アガーの原材料にも使われる「カラギーナン」、耐熱性が高く強いゲル状のものになる「ジェランガム」といった、ゲル化剤を使用したものも存在します。
これらを利用すれば、ジュース・抹茶などの液体や、チョコレートなどの個体でもプルプル系の食感を体現することができて、この食感を残しつつ様々な型にすることが可能です。
名前の通り、食べ物と食べ物をくっつけるものになります。
決してボンドでも、アロンアルファでもありません。(笑)
この食用接着剤の正体は、「トランスグルタミナーゼ」という酵素で、ヒトの皮膚にも多く含まれています。
このトランスグルタミナーゼはタンパク質架橋化酵素とよばれて、名前の通りタンパク質同士をくっつける効果があるのです。
つまり、魚だったらマグロの赤身と白身魚を、お肉なら豚肉と牛肉を人工的にあわせたものを作ることが可能になるのです。
トランスグルタミナーゼを使っても味覚や風味に影響しないので実際に、かまぼこのなどの練り加工食品や、成形肉をつくるときにも使われています。
前述で液体窒素・エスプーマ・ゲル化・食用接着剤の話をしてきましたが、これらの調理法を総称して難しい言葉になりますが「分子料理」や「分子ガストロノミー」と呼びます。
そして、この人工いくらは分子調理の基礎となっているものです。
言葉の通り人工いくらとは人工的に作られたいくらですが、この人工いくらが作られる原理を利用して様々なものが作られました。
原理としては、球体にしたい液の中に「アルギン酸ナトリウム(わかめや昆布などに含まれる水溶性の食物繊維)」を加えて溶かしておきます。
そして、乳酸カルシウム(カルシウム補給や、キシリトールガムの効果でよくある歯の再石灰化を促す成分)を溶かした水の中に入れると、膜を張って球体となる…わけです!
この原理を利用して、ドレッシングやフルーツソースなどを球体にして中を割ると溢れ出てくる、というオシャレな料理やデザートを作ることができるのです。
現代のIT・AI技術の進歩によって、飲食店も多大なる影響を受けています。
それでは、今存在する未来の飲食店、今後の飲食店はどうなっていくのか?についての考察をお話ししていきます。
飲食専門店へ行けば必ず店舗のスタッフから接客を受けますし、マクドナルドやケンタッキーといったファーストフード店でも注文をして、商品を受け取りますよね?
最近、流行っているウーバーイーツなどのフードデリバリーですら、対面で受け取る状況になるはずです。
しかしながら、昨今では対面接客のないシステムの飲食店ができました。
それは、東京の秋葉原にある「beeat sushi burrito Tokyo」という店舗です。
この店舗は日本初の寿司ブリトー(アメリカ西海岸が発祥のファストフード)専門店です。
店内を見てみると、LEDライトで近未来な雰囲気を醸し出したロッカーボックスが数字を割り振られてズラッと並べられており、そのロッカーの向かいにイートインのスペースがあります。
やはり、店内には店舗スタッフが見当たりません…。
※ロッカーボックスの後ろがキッチンになっているので、そこに調理スタッフはいるようです。
システムとしては、まずネットでお店の注文サイトへアクセスして、メニューを見ながら注文します。
支払いに関しても前払いのカードでのキャッシュレスで対応しており、価格はなんと時価!
注文したその日の素材や時間帯などでAIが価格を決めるそうです。
注文後は、出来上がりの時間の共有を受けて、店舗へ行く…という流れで
そこで、ロッカーボックスを開けて商品を受け取れば、利用完了です!
この営業スタイルが確立すれば、出来上がりの時間がわかるのでお客様は時間を有効活用できるほか、対面コミュニケーションが苦手な方も問題なく利用できます。
また、経営側に関してもシステムの確立により、人件費が大幅に削減されて利益率が上がることは間違いないでしょう。
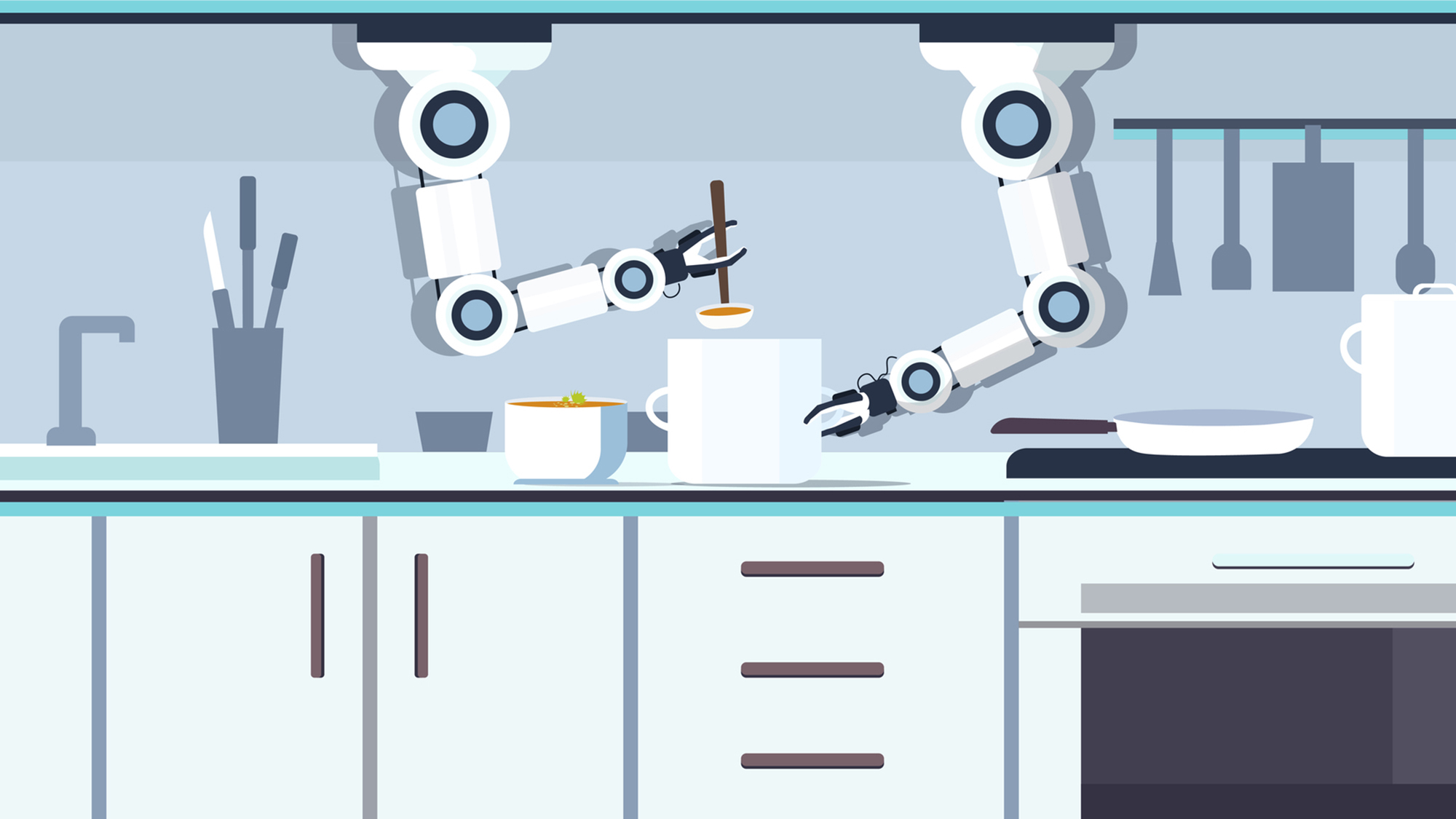
もちろん専門的な料理になってしまうと、現代の技術ではまだまだ人間には敵わないですが徐々に進化してきて、完全無人店舗として成立しているケースもあります。
それは飲食店、とまではまだまだいえませんが、アメリカのサンフランシスコに「Café X(カフェ・エックス)」というコーヒーショップがあります。
目の前には注文用のタブレットのようなものがあり、それで注文をすると、ロボットアームがバリスタに変わってコーヒーを淹れてくれるのです。
人件費だけではなく味に関しても、機械がおこなっているため人的ミスでよくある味のバラつきの心配もとくにありません。
そして日本でも、ロボットアームを使ったお店ができました。
千葉県のイトーヨーカドー幕張店内の「ポッポ幕張店」です。
このポッポ幕張店では、スタートアップ企業であるコネクテッドロボティクス株式会社が開発した、たこ焼きを調理するロボットとソフトクリームを製造するロボットを導入しています。
もちろん話題性もありますが、今後の品質安定と効率化を図るために、いち早く企業が取り入れたものです。
しかしながら、まだまだ課題点も多く、盛り付けや品質の最終チェックはまだヒトの力が必要となっており、完全無人化となるまではまだまだ先かもしれませんね。

前述の通り、今はまだヒトの力がない限り、完全無人化とまではいかないですが、技術の進歩が続く中で、いつかは実現されるものだと思ってもいいでしょう。
これによってロボットが料理を作り、店舗スタッフがいないで注文・会計ができるシステムが確立すれば、いよいよヒトが接客・料理をする飲食店がなくなってしまうのでは?と思います。
…ですが、答えはNOです!!
機械・ロボットは同じものを作ること・品質が変わらないものを作ることに関しては間違いないでしょう。
つまり、性能が変わらないのでいつ何時でも100%のパフォーマンスを実現することが可能ということです。
しかしながら、人間は努力をして、技術を磨くことができて、ロボットにはない「心」を持っています。
精神論的部分も出てきてしまうかもしれませんが、100%を超えた、120%、200%以上の力を出せる、もしくはその力を秘めているのです。
高級飲食店だけはヒトが接客する・料理をするものとして残るという予測を立てている評論家も多いですが、その中でいかに差別化ができるか?
この状況下でどう変わっていけるか?を考えていけば、生き残る術はあるはずです。
ヒトの気持ちがわかるのは結局、ヒトだけだと思います。
だからこそ、ヒトが接客・料理をする飲食店がなくなることはないのです。
いかがでしたでしょうか?
技術の発展はさまざまなシーンで影響を与える中で、飲食業界にも多大なる変化と影響を与えているのは間違いありません。
新しい調理技術ができることにより私たちフーディー(食べる人)の楽しみが増えます。
輝かしい未来ではありますが、その中でロボットが導入されることにより、今の飲食店がなくなってしまうかもしれない危機にも直面しなくてはいけません。
だからこそ他店の差別化、職人としての技術向上、ヒトが接客するというホスピタリティが今後の飲食シーンで生き残っていくためには特に重要になっていくでしょう。